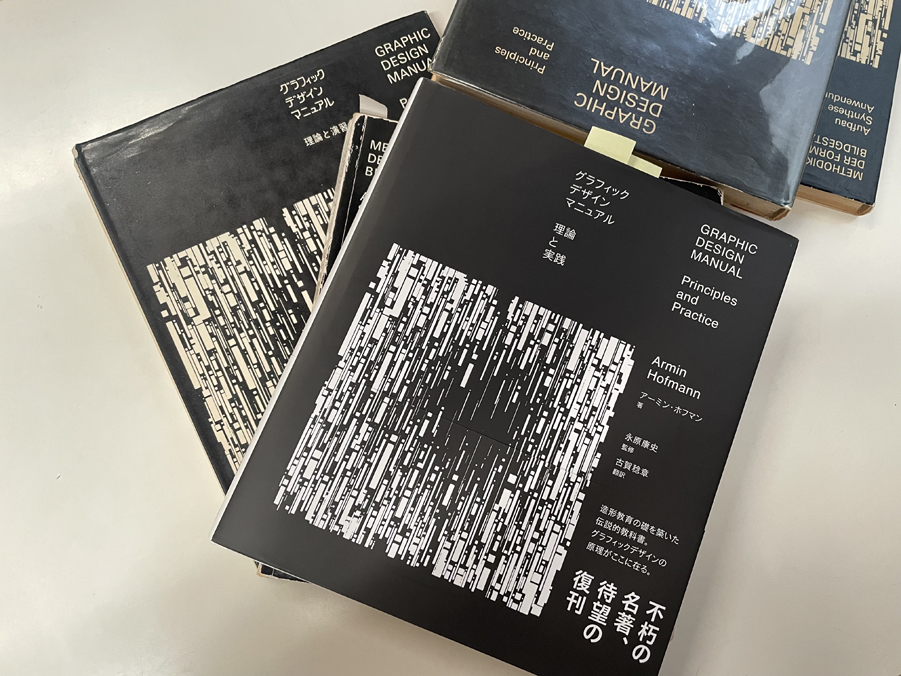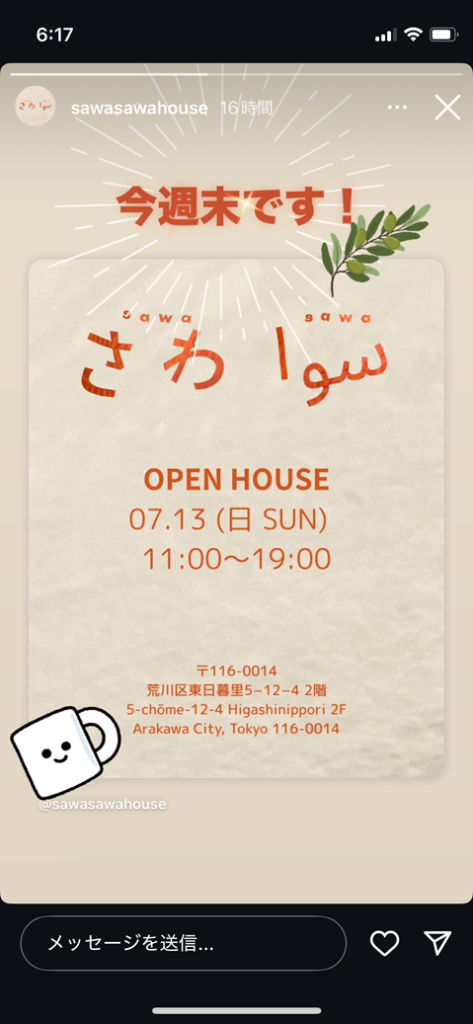一、大西定林造 姥口平丸釜
江戸中期の幕府御用を務めた釜師(初世浄林の弟の子)、江戸大西家の祖。具体的な歴史的建造物や場所は特定できないが寛永年間、古田織部に従い、父の二代浄清と共に江戸へ下向した定林が、江戸に留まって興した。釜の型は歯の抜けてしまった老女の口に似て、口縁部が内側に丸く落ち込んで、つぼまった形の口造りなので、姥口と呼ばれている。浄長(十三代清右衛門)極
一、三浦乾也造 竹図四方蓋置
明治初期の江戸の陶工。江戸末期には伊達侯に招かれて松島寒風沢に造船所を起こし、明治に入り小田原に窯を開く、その後東京に戻って葛飾区小菅で煉瓦を製造。のち深川高橋付近に陶窯を築き、1875(明治8)年より向島長命寺内で製陶した。陶法は尾形乾山風を慕って、西村貌庵から乾山伝書を授かり多く乾山作を模倣した。「乾也玉」と呼ばれた根掛けやかんざしの珠が流行った。乾山を称しなかった理由は謙遜からとも、独自の見識からともいわれている。
一、輪王寺宮天真法親王筆 和歌色紙
「晴ゆくか雲と霞のひまみえて雨ふきはらふ春の夕かぜ」(風雅和歌集、徽安門院)古筆宗家6代の古筆了音が認めており、天真法親王は後西天皇の皇子で、乾山を庇護した公弁法親王の兄富にあたる。