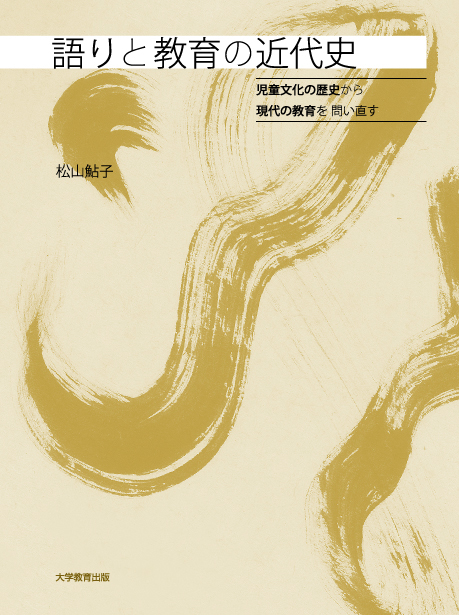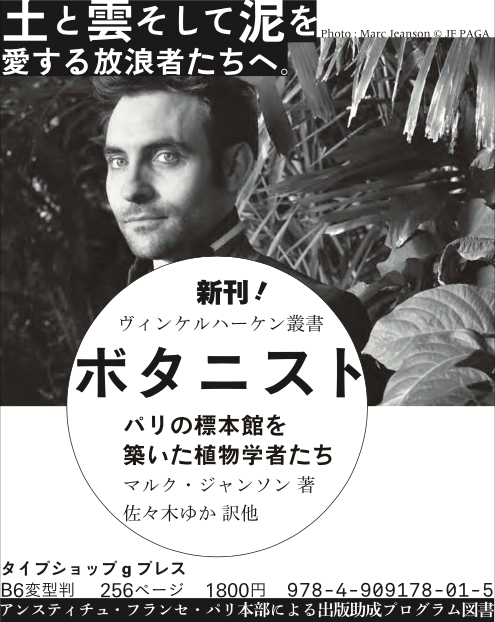今月号の記事はとても良い。しびれる。猶有斎が即中斎のを引用している。1939年雑誌『わび』に掲載、あまりに共感したので引用させていただく。
「茶道においては、完全なものより不完全なものにその貴さを見出さんとする傾向がある。具足したものよりも不具足のもの、満足せるものより不満足なものにより以上の価値を見出す態度である。これは侘びという精神にも大いに関連してくるが、これと相関して考えられるのは、近時物資の節約が叫ばれる折柄、各人がお互いに自粛してその目的を達せねばならない。不自由を忍ばねばならない。しかも不自由を単に不自由として忍だけではいけない。不自由の中に自由を見出さねばならない。不満足の中に満足を覚えるのである。不自由を単に不自由として消極的に耐え忍ぶのではなく、不自由の中に積極的に満足を感じて、充足を覚え楽しさを感ずるのである。これが茶道の態度である。
平凡なことを平凡にやってのけるには、平凡以上の力がいる。平凡なことを平凡にして、しかもそこに自らの妙味を見出すことは、一朝一夕ではできない。これを悟れば、すべての日常のことに無限の滋味が湧いてくる。一度縁あって茶道にいそしんだ人々は、茶道の修練によって、この境地に達して頂きたいと思う。」
昔から、茶の湯の宗匠とは何者なんだろう、、、
僧侶のようで僧侶ではない。
武士のようでそうではない。
貴族のようでそうではない。
芸術家のようでそうではない。
演出家、演じ手のようでのようでそうではない。
料理人のようでそうではない。
書家、水墨画家のようでそうではない。
職人のようでそうではない。
教師のようでのようでそうではない。
目利き、鑑定士のようでそうではない。
花は生けるが華道家ではない。