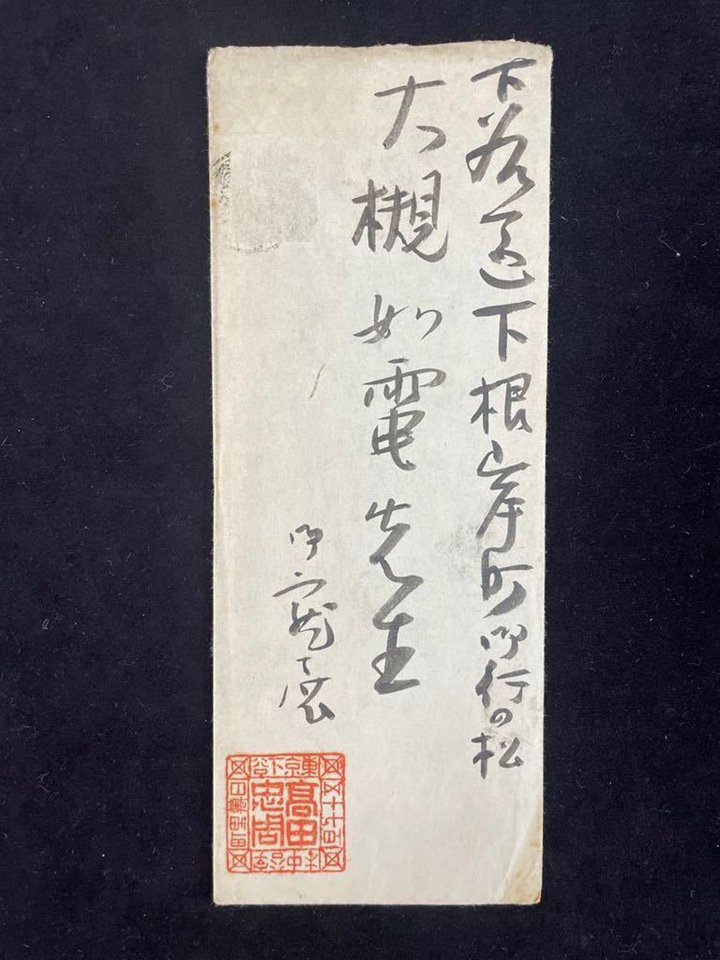とうとう最終回が終わってしまいました(ロス百音)。当初、母と見出した時はこのような気に留めるドラマになるとは、正直思っていませんでした。震災にあった人で同種の心に傷を負った者でなければ、理解できないかもしれない部分が多く含まれていることに驚いています。それにしても、よくこのように毎日何かしら引っかかるように朝ドラに仕立て上げたものと絶賛したいです。数年前に三陸の若い海女さんのドラマもありましたが、同じように東北の被災をテーマにしていたのに比較にならないほどの出来だと思います(話題だけで、あまりにくだらないので見ていませんでしたが)。
実際ぼくの場合は、この主人公モネとは逆のローケーションなので、また違った複雑な内面の部分があると思いますが、とても興味深いです。
1.
住人として被災しているが、他の人と違って、偶然その時にその場にいなかった。=同じ被災者でも完全に線引きされます。後で、駆けつけたが、明らかに周囲の人とは違う(差別を受けました)。
2.
ぼくの場合は、その時以降、上司からパワハラを受け続けます。そのような中、当時の「市民大学の責任者」でうちの大学の代表でした。市役所の(災害後なので廃案にするつもりでいた)担当者と市内にある他の二大学の担当者と尽力して、なんとか続けることができました。「何か被災者のために現地(ぼくも住人の一人と思っていましたが、そうではない)でできないか」を探していた毎日。
3.
最終的には、退いて同じように故郷に戻ろうと決心します。ぼくの場合はモネとは逆に東京に。創設に参加した大学を後に。しかし裏切り者扱いを受ける。
4.
そして、本題:教師と現場の話。ぼくは地震と同時に教室で教えていたわけではないので、家族と比較はしませんでしたがしかし、被災地での教員は実にきつい。正直逃げ出したくなる。被災後じわじわと、違った意味で現れてくる恐ろしさ。誰にも話せない。
今となっては、大学で教えていたことは遠い昔のことで、今の自分の生活と切り離しているつもりでいたが、そうではないとまた再び再確認し、いろいろと気づかされた。あの経験がその後の人生でいろいろな意味でよかったのだと信じるしかない。放送されていた毎回、忘れかけていた懐かしい細かい心の動きを感じることができて、とても有意義な半年でした。「おかえりモネ」に多謝。それと気象に関わるという職業の不確定さも相まって興味深かった。俳優も全ての方がとても良かった。ぼくが朝ドラでこのように感じたのは本当に初めて。