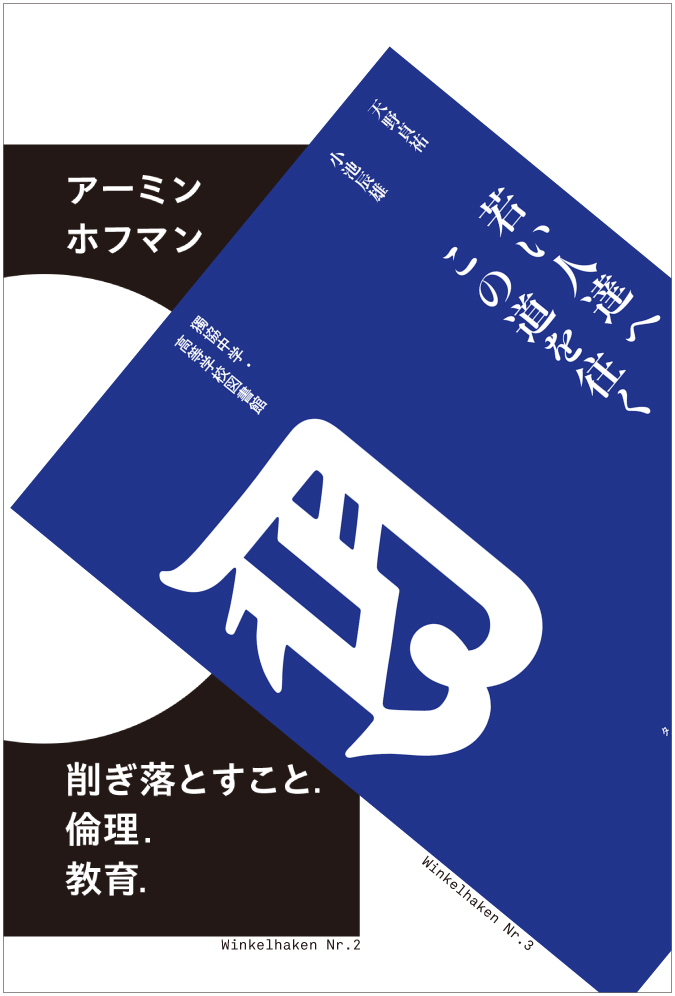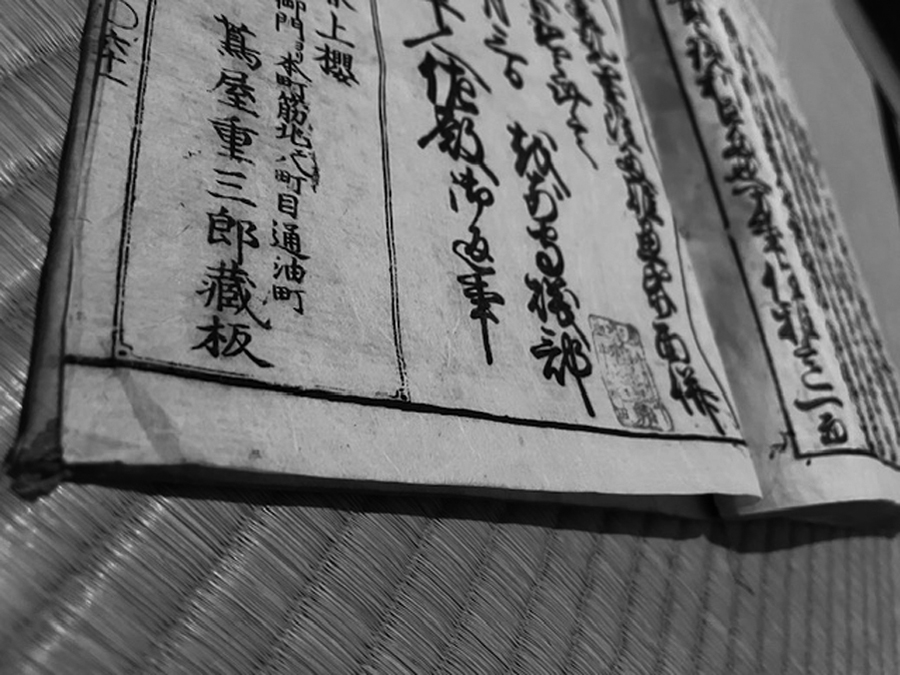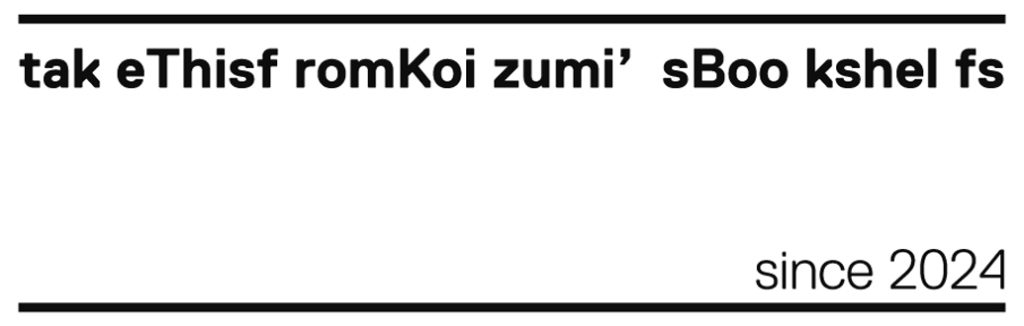大槻の近傍図(明治34)より45年前の図(安政3)、先祖の梅屋敷が載っている。国立国会図書館蔵。
-江戸切絵図全体図
https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/iiif-curation-viewer/?curation=https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/1856/ndl.json&mode=annotation&lang=ja
-現代位置合わせ地図
https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/georef/
-地名一覧
https://codh.rois.ac.jp/edo-maps/owariya/28/
28-090 梅屋敷=小泉家
28-088 三島大明神
28-076 笹の雪
28-074/75 金杉村新田
音無川沿いに 百姓町 が続き
28-084 此辺一面根岸ト云
その付近に
28-085 円光寺=藤寺
28-082 西蔵院
28-083 永称寺
28-086/087 宮様家佳居
28-081 不動尊五行松=御行松
28-080 道ナシ横丁
28-079 下谷
28-078 藥王院
28-029 公春院
28-028 真正院
28-027 円通寺
左手には池田播磨守大名屋敷:
28-031 宗対馬守
28-032 大関信濃守
28-033 加藤大蔵少輔
28-030 石川日向守
三ノ輪付近まで。
ウチより上流へ、王子方面に向かうと:
28-073 社家
28-089 御隠殿
28-072 善光寺=善性寺
28-091/092 植木屋
28-093 芋坂ト云
28-095 天王寺
28-239 妙余寺(現存しない)
28-240 長善寺(現存しない)
28-071 ◯下谷中ト云 志賀
28-111 浄光寺 梅ノ天神
28-070 下日暮里ト云新堀村百姓家
28-115 植木ヤ
28-116 松平越後守
28-069 正覺寺
28-068 宗福寺
28-067 此辺足立群三十六ケ村組合新堀村 但シ下日暮ノ里ト云
28-066 興樂寺 六アミタ四番
28-117 道灌山
28-065 西国二十九番丹後松尾寺移 東覚寺 九品仏仁王尊二番八幡宮
この裏で二手に分かれ、日暮里の裏根津方面に
28-064 西行庵 普門寺 西国十一番札所
28-063 常養寺
28-062 光明院薬師堂
28-061 田畑村早川ト云
28-060 早川ト云中田畑村
28-059 別当大龍寺八幡宮
28-058 仲台寺
28-057 下田畑村
此道六アミダ三バン西ケ原エ出ル
28-056 王子権現 深越藤助
28-054 六アミタ一番 西福寺
是ヨリ王子稲荷ノ向エ出ル